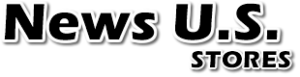すべての上長やマネージャーは、労働生産性の真実について知る必要がある。オフィスにいるだけで生産性が向上するわけではないことを。The Straits Timesが報道した。
先月末、シンガポール政府から在宅勤務を標準化するようにという勧告が出たにも関わらず、多くの雇用主がスタッフにオフィスに戻るように求めた。彼らは従業員が1日の仕事を自宅でできるかどうかが信用できなかったからだ。
上長が信頼できない怠け者を沢山雇った可能性があるものの、従業員としても自分の役割を果たして信頼を勝ち取る必要がある。そうしなければ昇進やボーナスを受け取ることができないかもしれない。最善を尽くしたなら、別の仕事を探すことも必要だ。
1. 身だしなみと才能の発見
多くの専門家が口を揃えて主張するのは、パンデミックを通じて従業員が自宅から非常に多くの仕事を達成できると気付いたことだ。例えば今読んでいるThe Sunday Timesは、去年の初めからほぼ完全に在宅勤務のジャーナリストによってまとめられている。
STのジャーナリストは在宅勤務が世界的なトレンドになるずっと前から、外国特派員やコピー編集者として”世界中の自宅”で仕事をしているという。毎日の具体的な目標があり、誰もが自分の役割を果たせば十分に可能なのだ。結果さえ出せば上長が現在の居場所を尋ねることもない。
在宅勤務は販売やプロジェクトの目標などを全員に与えれば機能する。誰もが自分自身で仕事をすることで、社内政治の悪しき習慣や怠惰でパフォーマンスが低い人を減らすことに繋がる。
2. コストと時間の節約
かつては高級オフィススペースを多く占めていた経営幹部の部屋だが、もはや今のトレンドではないと言える。グローバル金融機関の多くのトップは部屋をオープンなオフィスや会議室に変えた。それによりオフィススペースが削減されれば、年間数百万ドルの賃貸料や光熱費の節約に繋がるからだ。
例えばスタンダードチャータード銀行は、今年の終わりまでに世界中の上級スタッフが使用する881のオフィス全てを会議室に変えることを目指している。最高財務責任者のAndy Halfordは「専用オフィスのコンセプトは急速に歴史に委ねられ始めている」と語った。
海外出張を減らすこともできる。直接会うことが絶対的ではない限り、多くの経営幹部は世界中を飛び回ることをせずバーチャルな会議を好む。
3. 新しい働き方
一部の従業員は、在宅勤務は終了のタイミングが難しいことから長時間労働を意味すると不満を漏らしている。定例のオフィス会議が変更されておらず、通常の仕事を営業時間外にやる必要が生じている。
したがって、上長は全体的な作業プロセスも検討して、従業員が生産性の向上とワークライフバランスという2つの重要な結果を達成できるようにする必要がある。
例えば定期的なチームミーティングを開催しないこと。明確な目的と結果がない限り、会議は生産的ではないことを知る必要がある。様々なプロジェクトについて話し合い、意見を求めたい場合は関連するメンバーとのみ短い会議を実施すればいい。
従業員が在宅勤務をすることは、独立したオペレーターへの昇格を意味する。時間をどのように過ごすかを細かく制御できる。目標と成果について上長と話し合うことで、どのように仕事をするかを自由に決めることができるだろう。9時から5時までのルーティンにとどまらないかもしれないが、最も生産的な方法を見つけ出せるはずだ。
在宅勤務は世界的に見てもさほど定着はしていない。先進国だろうが途上国だろうが、ケースバイケースでオフィス出社を求める企業もまだまだ多い。完全な在宅勤務としてしまうと、上長や他のメンバーから対面で学べる機会が減るという懸念もある。週1や週2、あるいは月1回というような程よいペースの出社が望ましいように思える。✒